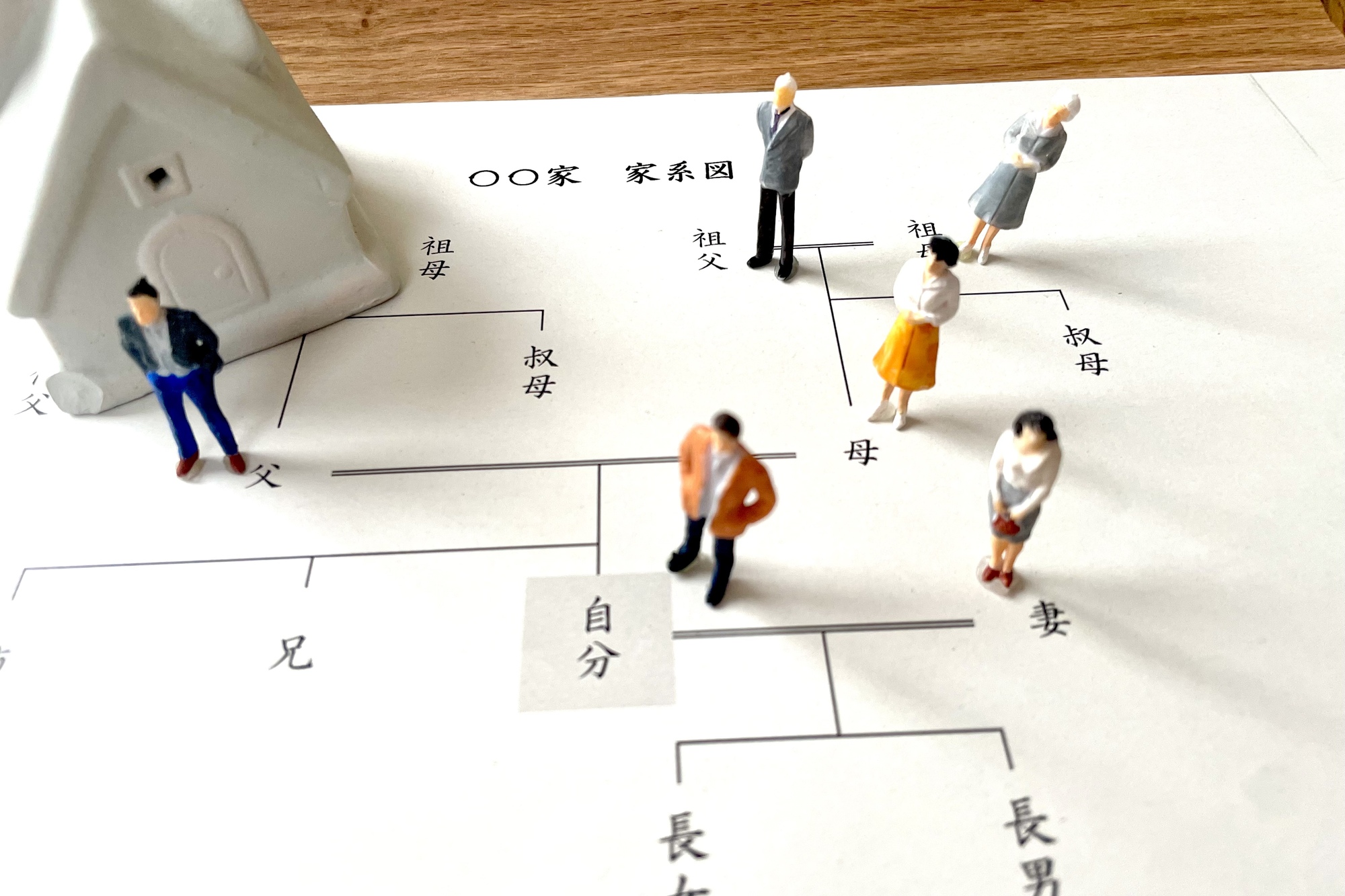不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
確定申告と顧問税理士の役割
最近は、会社勤めをして給料をもらいながら副業で収入を得る方が増えています。不動産を購入して賃貸することで家賃収入という副収入を得る方もいます。それに伴い、税金の手続きが年末調整だけでは済まなくなり、確定申告をしなければならなくなった人もいるのではないでしょうか。ただ、いきなり確定申告をすることになっても、何から始めたらいいのか、何をどうしたらいいのかわからない方も多いはずです。そういうときに相談できるのが税理士です。今回は賃貸不動産に関わる不動産所得について、税理士への依頼方法やメリットを説明します。
税理士には何を頼めるのか
税理士資格は国家資格の一つです。税理士資格を持つ人は、税理士として納税者の税金に関する相談や税務署などへの対応を代理することができます。納税者は、申告書の書き方などの質問のために税務署に行くことはできても、節税対策の相談やシミュレーションは受け付けてもらえません。税理士はそのような相談も含めて、納税者が正しく税金を計算する手助けをするのが仕事です。
税理士には税金だけでなく、お金に関する様々な相談をすることもできます。賃貸不動産を購入する際は、購入金額と家賃収入、経費のバランスを計算して、税金の試算をしてくれます。そして、税理士は購入する不動産が果たして予定通りの利回りになるのかどうかを検討し、購入を決める参考になるような材料を作成してくれるのです。
また、購入した後の確定申告までの間にしなければならない書類の集め方や保存方法、帳簿の付け方などの手引もしてくれます。税務署への開業届などの届け出の提出は、税理士が作成の上、納税者が確認した後に税理士が提出します。
税理士は、日本全国に登録者数で79,696人、東京だけでも23,732人の登録者がいます(令和3年8月31日時点)。主に税務署の管轄ごとに税理士会の支部があり、税理士会の支部へ行けば税理士を紹介してもらえます。また、知り合いに自営業をしていたり、会社を経営していたりする方がいれば、その方が税理士へ依頼しているケースが多いです。そういった方に依頼している税理士の様子を聞き、紹介をしてもらうと安心です。
税理士と顧問契約を結ぶ場合には、契約前に税理士報酬の確認をして、追加でかかる費用などもしっかり確認しておきましょう。
不動産所得を計算する上での注意点
では、税理士に依頼して不動産所得の計算をする場合、どのような作業や注意点があるのでしょうか。不動産所得の計算は、不動産収入になる受取家賃や不動産収入から控除できる経費の集計が主な作業になります。そのためには何が不動産収入になるのか、何が経費になるのかを知ることが大切です。
1.不動産所得の収入
家賃の入出金等を不動産管理会社へ任せて、毎月の入金と出金の精算一覧などをもらっている場合は、収入の集計の際に精算一覧が必要になります。精算一覧は無くさないように大切に保管しておきましょう。ただ、精算一覧にある入金の中には収入では敷金や保証金などの不動産収入にはならないものが含まれていたり、入金がないために一覧表に出てこなかったりしても、不動産収入になるものがあります。
下記2点に注意しましょう。
◯家賃の滞納などで未入金になっている家賃は、入金がないために精算一覧に記入されていないことが多いです。しかし、もらうべき月の家賃は入金があったかどうかに関係なく、その年の不動産収入に含めなければなりません。
◯オフィスの不動産の契約には、保証金の償却というも契約がある場合があります。保証金償却があっても金銭の動きはありませんが、返還をしないこととなった償却額は不動産収入にしなければなりません。これも入金がないため、管理会社からくる精算一覧には記入されていない場合が多いです。更新の際には、更新書類を確認するようにしましょう。
2.不動産所得の経費
精算の一覧表に書いてある出金には、不動産所得の経費にならないものや全額をその年の経費にできないものがあるので注意が必要です。
◯敷金や保証金の返還(支払い)は預り金の返還にあたるため、預かったときも返したときも不動産所得の計算には含めません。
◯修繕費のうち、資本的支出といって、建物の使用期間を延長させたり価値を増加させたりする支出は減価償却計算の対象になるため、全額が支出した年の経費になりません。基本的には法定耐用年数を使って、耐用年数内で按分して経費にします。
◯火災保険料などで1年を超える長期契約で加入した場合には、毎年の対応する月数分だけを計算して経費にします。
以上のように、不動産管理会社からくる精算一覧だけでも内容ごとにどのように扱うかを検討する必要があります。この他にも固定資産税を現金で支払ったり、賃貸物件の共用部分の電気代を自動引落しで支払ったりした場合など、不動産所得の計算上で認められる経費にはさまざまなものがあります。逆に所得税や住民税は経費にできない税金として決められている支出もあります。
さらに、経費にするためには、領収書などの書類の保存も必要です。税理士との顧問契約を結ぶことで、経費にできるかできないかだけでなく、経費にするために必要な書類の保存についてのアドバイスも受けることができます。
税理士に依頼できること
税理士と顧問契約を結んで依頼する仕事は、収入や経費の集計作業や税務相談が思い浮かぶと思いますが、その他にも下記のような業務を依頼することができます。
1.申告書の作成と提出
税理士と顧問契約をすると、基本的には申告書の作成と提出はすべて任せることができます。税理士は会計ソフトや申告書作成ソフトを使用して、収入や経費の集計と帳簿の作成、申告書の作成を行っています。会計ソフトの入力は一見簡単なように思えますが、複式簿記を使って正確な帳簿の作成するのは、意外とハードルが高く、正確な帳簿が出来上がらなければ、せっかくのデータ入力が無駄になりかねません。
また、多くの税理士が申告書作成ソフトと連携した電子送信の専用ソフトとを使って、e-TaxシステムやeLTaxシステム経由で役所へ申告書の送信(提出)をしています。納税者に代わって、税理士が申告書の代理送信を行えば、申告書を提出するために税務署で並ぶ必要がなくなります。
2.税務署対応
税理士との顧問契約の中に税務代理を含めると、税理士は税務署等へ「税務代理権限書」を提出して、税務署等に対して納税者の代理人となります。これにより税務署は税務調査の連絡などを、基本的には代理人である税理士に連絡をすることになります。普段でも税務署から申告書の内容についての簡単な問い合わせが入る場合があり、その連絡も税理士へいくので、電話だけで問い合わせの対応が終わってしまうことがよくあります。
また、税法とその取扱いは難解であるため、税務署からの申告内容の相違の指摘を受けた場合に、対応に困って内容を理解しないままに修正申告を提出するケースが見受けられます。しかし、税理士を代理人とすることで、税務署の指摘事項は税理士を通して説明を受けることが可能になり、本当に相違があったかを検討し、修正申告の提出に応じるかどうかなどを税理士と話し合って決めることができます。
3.青色申告特別控除のための貸借対照表の作成
通常の不動産所得の青色申告特別控除は10万円ですが、不動産賃貸を税務上でいう事業的規模で行っている場合には、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告書の青色決算書に損益計算書だけではなく、貸借対照表も添付し、e-Taxにより申告書の提出をしなければなりません。貸借対照表は、簿記の知識がなければ作成は難しく、慣れずに会計ソフトを使い始めると、経費の二重計上をしてしまうことや普通預金の残高を合わせられないなど、貸借対照表の作成完了まで至らないケースに陥りかねません。
税理士へ会計データ入力等の依頼をすると報酬が心配になるかもしれませんが、取引数や事業規模にもよりますが、税理士報酬は青色申告特別控除の65万円控除以内に収まる場合が多いでしょう。報酬は、依頼する前によく確認してください。
まとめ
餅屋は餅屋ということわざがありますが、税務に係ることは税理士に相談をしながら進めていくに越したことはありません。ただし、税理士もいろいろなタイプの人や得意分野があるので、もしスムーズなやり取りができない場合には他の税理士へ替えることも大切です。また、どんな内容を依頼できるかは税理士によっても違いますので、契約前に確認してください。
執筆者:
須栗 一浩
税理士
税理士法人エムエスオフィス 代表
1995年に税理士登録し、これまで個人法人の関与先クライアントは500件をこえる。個人事業の開業から、法人設立、相続税まで含めたトータルのコンサルタント業務をおこなう。企業のICT化も推進し、クライアント企業への導入も進めている。ファルクラム租税法研究会研究員

無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search