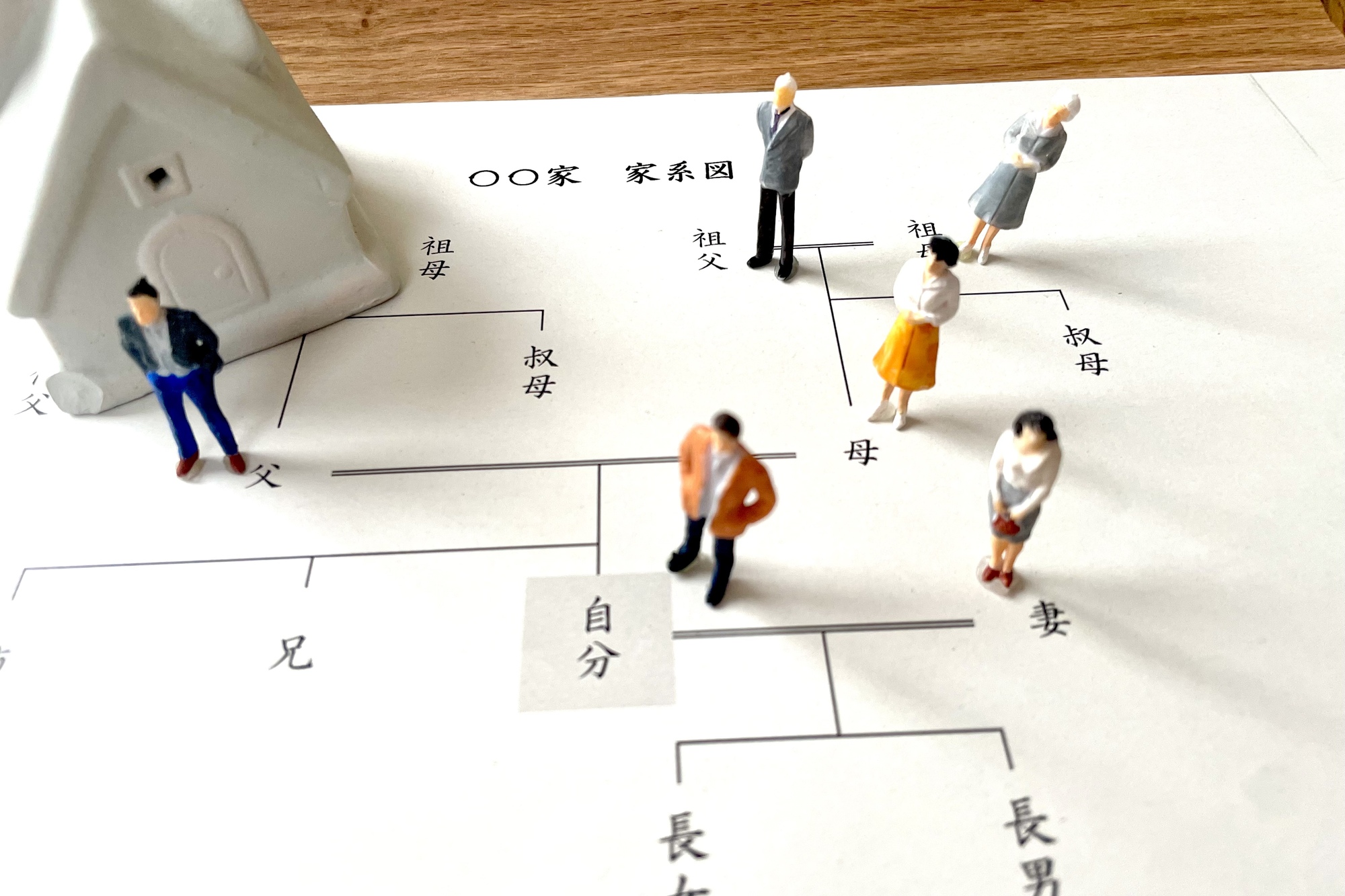不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
“相続を争族”にしないために。民法改正で変わる遺言作成と不動産相続のポイント
「相続」は誰にでもいずれ訪れます。
人口動態統計によれば日本全国で昨年は130万人以上の人が死亡し、その数だけ相続が起きています。
そして、相続は“争族”といわれるように、しっかりと準備しなければ大きな争いを引き起こします。
2020年の民法改正に伴って、遺言の作成方法や相続物の取扱いにも変化が見られ、“相続を争族”にしないためにもポイントを抑えておいたほうが良いでしょう。
特に不動産相続は複雑で、注意点を知っておかないと取り返しのつかないことになりかねません。
今回は、不動産相続で争いが起きる理由の他、民法改正によって変化した遺言の作成方法や相続不動産の扱いなどについてご紹介します。
不動産相続で争いが起こるワケ
相続の中でも特に争いやすい不動産関連ですが、その理由は他の財産と異なる次のような特徴があるからです。
・分割できない
不動産は預貯金や株式のように分けられないのが特徴です。確かに法律上、不動産には「共有」や「分有」という考え方はありますが、現実の土地や建物はケーキのように「3つに分けて持ち帰る」ことなどはできません。
・金額が大きい
一般的な相続では、不動産が相続財産の中で大きな割合を占めます。
・換金しにくい
財産をお金に換えるには売却しなければなりません。これには数か月の時間がかかってしまいますし、最近では空き家が社会問題となっているように、「不動産を売りたくても売れない」なんて話もよく聞きます。
・持っている限り維持費がかかる
所有しているだけで維持費がかかるのが不動産の特徴です。毎年の固定資産税に町内会費、台風や地震による修理費用もかかります。そうしているうちに50年に1度訪れる屋根の葺き替え工事では百万円単位の費用がかかります。マンションなら管理費や修繕積立金が重い負担となるでしょう。
不動産が“負動産”といわれる現代、不動産を持っている人が遺言を残さず死亡してしまうと、残された配偶者、子の兄弟の間で「不動産の押し付け合い」が始まる可能性が大です。マイホームを持っている人は生きているうちに遺言を残し、不動産は誰か1人に相続させ、ある程度の維持費もつけて残すようにしましょう。
このように、不動産は相続の中でも特に取扱いが難しいため、遺言書でしっかり「誰に何を残すのか」を定めておく必要があります。
民法改正によって、遺言作成が以前よりも楽になったため、不動産相続で争いを生まないためにも、亡くなる前にしっかり遺言書を用意しましょう。
では次に、民法改正によって遺言作成がどのように楽になったかをご紹介します。
民法改正で大きく変わった自筆遺言の方法
現行の民法は明治29(1896)年に成立した法律で、序文など一部はいまだにカタカナで書かれています。その後改正を重ねて、2020年にも大改正が予定されています。
そのことをいまだに知らない人が6割以上いるという調査結果もありますが、それに先立って遺言の方法がすでに改正されています。
「遺言」と聞くと、縁起でもないとか、面倒そうとか、できれば避けたいといった気持ちが先に来てしまいがちですが、実は、今の遺言はとっても書きやすくなっているのです。
例えば、以下のようなことができます。
・財産目録をパソコンで印刷してもOK
これまで遺言書はすべて自筆しなければなりませんでした。遺言書を書くのはお年寄りが多いでしょうから、手が震えたり筆圧が小さかったりして、お年寄りが長文を正確に書くのは実に大変なことでした。それが今では、本文は自筆ですが、財産目録をパソコンで作成して印刷し、各ページに署名捺印すれば、それで有効な遺言書になります。
・財産目録はコピーでもOK
財産目録の様式は、署名捺印の他特に決まったものはありません。自分以外に他人が作ったフォーマットでもいいですし、預金通帳のコピー・土地建物の登記事項証明書・置物の写真・ネット証券の画面のハードコピーなど、書面になるものならおおよそなんでも使えることになります。
・遺言書本文の記載が最低限に
依然として本文は自筆しなければなりませんが、目録の様式は自由が利くようになりました。そのため、本文は「〇〇に別紙目録第1記載の財産を相続させる」「〇〇には別紙目録第2記載の財産を相続させる」…と最低限のことを書いておけば良く、あとは目録を編集して作ることができますのでお年寄りでも負担が小さくなりました。
・書換えが簡単にできる。
気が変わった場合でも、目録を編集するだけで遺言書の書換えが比較的簡単にできます。
・来年から法務局で保管できるようになる。
これまで、書いた遺言の保管場所は、仏壇の奥の引き出しなどが一般的でした。2020年からは、法務局に遺言書保管所という場所ができ、遺言を保管してもらうことができます。
また、これまで、遺言の作成は、公証人と証人2名の合計3名の立会いのもと行われる「公正証書」と呼ばれる方法が主流でした。今まで遺言はハードルが高かったかもしれませんが、これからは証人なしでも作成できる自筆証書遺言が一般的になる可能性があります。
遺言書の作成は手間と時間を要するものでしたが、ここまでご紹介した改正によって「作成のハードルが低くなり、誰にとっても作りやすいものへと変化」しています。
民法の改正で注意すべき「相続不動産」の扱い
民法改正で遺言の作成に関してはハードルが下がりましたが、中には取扱いに注意すべき内容もあります。それが「相続した不動産の扱い」について。どのような部分に関して注意すべきか、夫婦と子ども1人の家族の事例をもとに解説します。
このような場合、改正前はたとえ登記が他人に移っていたとしても、不動産の半分を所有している母親が取り戻そうとすれば戻ってくるはずでした。(昭38年2月22日最高裁判例)
しかし、改正後は同様のケースでも“二重売買(1つの不動産を2人が別々に売ってしまうこと)”と同じ扱いになり、登記を先に備えたほうが所有権を主張できるようになったのです。子どもから共有不動産を購入した人が登記してしまうと、もう母親のところに戻ってくることはありません。
これは何を意味するかというと、“相続した不動産は一刻も早く相続登記をしなければならない”ということです。ぼやぼやしていると、悪い子どもや兄弟に勝手に売却されてしまうことがある、ということなのです。
参考:裁判所「最高裁判例」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53697
まとめ
今回は、改正民法のごく一部を紹介しました。
2019年、2020年と民法は大きく変わっていきます。しばらく混乱もあるかもしれませんが、相続をスムーズに完了させ、争いを引き起こさないためにも、新しいルールについて知っておく必要があるでしょう。
参照:厚生労働省「平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/dl/02_kek.pdf
参照:法務省「法務局における遺言書に関する法律について:」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html」
中山 聡 不動産鑑定士・一級建築士
富山県生まれ。東京大学医学部を卒業後、三井住友信託銀行、近畿大学工学部、株式会社アイディーユー、早稲田大学大学院ファイナンス研究科招聘研究員、チームラボ株式会社等にて、インターネットで不動産取引ができる環境づくりを中心に、研究開発室長、経営監査部長として事業開発、M&A、事業会社管理に携わる。 現在、わくわく法人rea東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ株式会社代表取締役。執筆・著書に、『闘う!空き家術(週刊住宅新聞社)』『新訂 闘う!空き家術(プラチナ出版)』『空き家管理ビジネスがわかる本(同文館出版DO BOOKS)』『ビジネス図解 不動産のしくみがわかる本(同)』『はじめてでもわかる不動産金融工学(雑誌「ルクラ」連載)』『不動産カウンセリング実務必携(日本不動産カウンセラー協会刊・共著)』などがある。
| ・事例 遺言を残さず夫が死亡すると、夫の財産は妻が2分の1、子どもが2分の1を相続することになります。不動産は2人の共有になります。しかし、子どもがお金欲しさのあまり、自分1人が不動産のすべてを完全に所有しているふりをして、第三者に売却してしまいました。 |

無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search