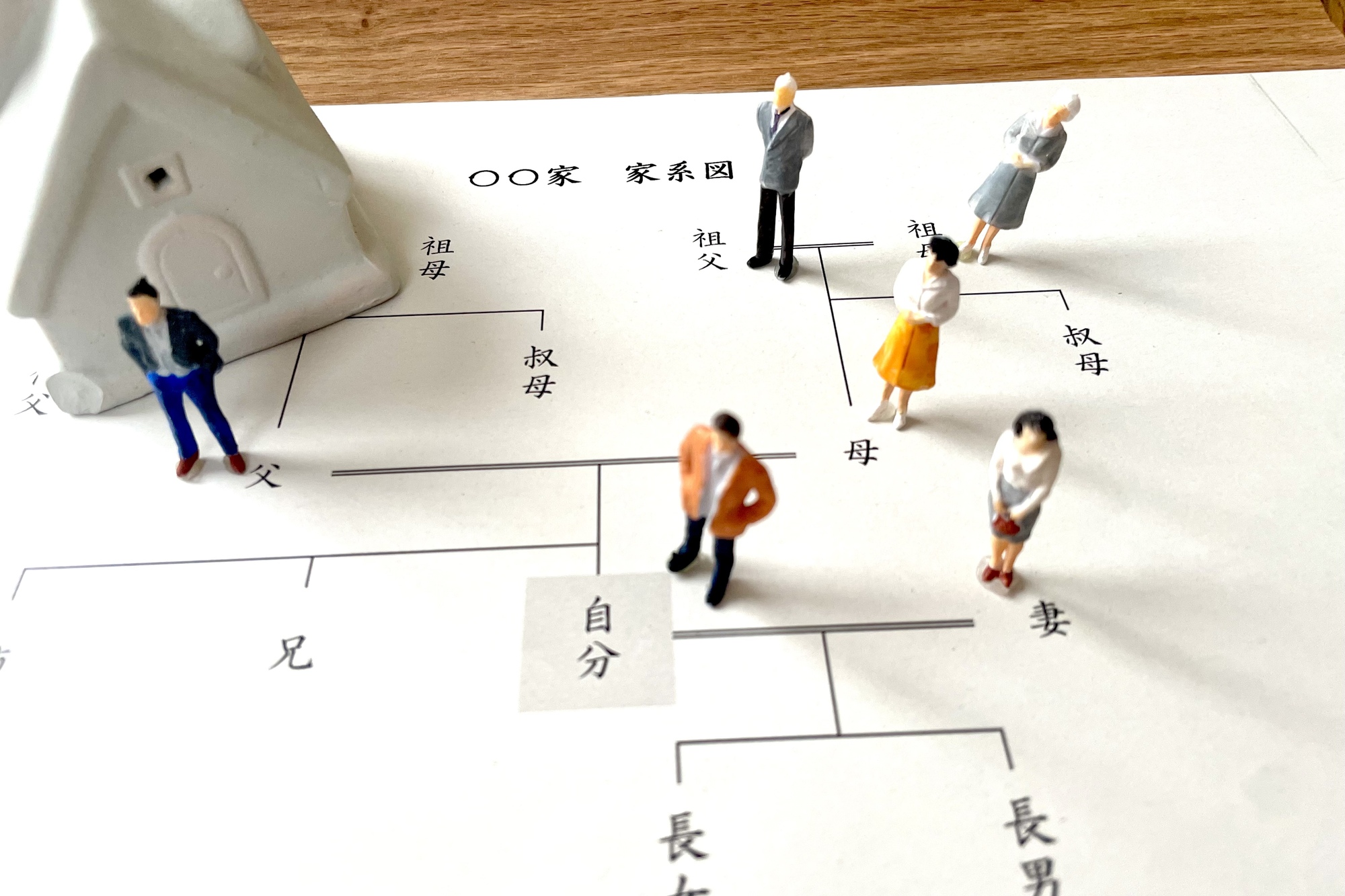不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
不動産査定 自分で査定額を計算してみよう!
不動産の売却を検討している場合、今の相場ではどれくらいの査定額になっているのか気になりますよね? ただ、はっきり売却すると決めてないのに不動産仲介業者に査定を頼むのは気が引けるという方もいるかもしれません。そんな時は自分で査定額を計算してみましょう。今回は、簡単な不動産査定の方法を説明します。
まずは査定に必要な情報を整理する
売却を検討しているのが自宅の場合、築年数や面積などはなんとなくわかっていても、細かいことまでは知らない方も多いはず。ましてや親の家を相続し、売却を検討しているなどの場合はわからないことだらけでしょう。そこで、査定に必要な情報を整理する作業から始めましょう。
まず用意してもらいたいのが、不動産の全部事項証明書と固定資産税・都市計画税の納税通知書です。全部事項証明書は一般に登記簿謄本と呼ばれているもので、登記記録を証明するための書面です。全部事項証明書は土地と建物に分かれており、所在や地番、家屋番号、地積(土地の面積)、床面積、新築年月日などが記載されています。土地が何筆かある場合は筆ごとに全部事項証明書があります。敷地権化されたマンションの場合は建物の全部事項証明書だけで問題ありません。
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、不動産が所在する市区町村から課税明細書とセットで送られるものですが、この中で重要なのが課税明細書に記載されている評価額です。そこから基本的な数値として、土地の全部事項証明書から地積の合計、建物の全部事項証明書から床面積の合計、築年数、課税明細書から土地の評価額の合計、建物の評価額をまとめて整理しましょう。
次に立地条件に関する情報を整理します。まずはGoogleマップなどを使って最寄りの駅からの徒歩での距離を測りましょう。最寄り駅が複数ある場合はより大きな駅、利用者が多い駅からの距離を計測してください。一般的には徒歩10分程度(徒歩1分=80mとして約800m)までが徒歩圏内とされ、10分を超えると需要が少なくなる傾向があります。
住宅市場をもとに相場を把握する
次に、査定のベースになる住宅市場の情報を集めます。国土交通省の「地価公示」は一般の土地取引の指標となるもので、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格が公示されます。その地点の鑑定評価書が開示されており、年間の変動率、採用された取引事例の取引価格を見ることができますので、変動率がプラスとなっているか、マイナスとなっているかをチェックします。変動率がプラスの場合は上がっている可能性が高く、マイナスの場合は下がっている可能性が高くなります。いろいろな地点をみていくと、価格や変動率が違うことがわかるでしょう。一方の都道府県の「地価調査」は毎年7月1日時点の価格です。
地価公示や地価調査は土地の相続評価や固定資産税評価の基準となっており、大変参考になる情報ですが、地点数が限られていますので、最寄り駅、駅からの距離、用途地域、容積率、道路の幅、地積ができるだけ似た条件の地点を探してみましょう。
「相続税路線価」は相続税や贈与税の評価をする場合に適用されるものです。地価公示と同じく、毎年1月1日時点の1㎡当たりの土地の金額ですが、概ね地価公示価格の8割程度で、単位は千円単位で表示されています。相続税路線価が200千円だと200千円÷0.8=250千円が公示価格水準になります。不特定多数の人が利用できる道路ごとに設定されていますので、地価公示よりもかなり細かな範囲で相場を把握することができます。
「不動産取引価格情報検索」と「レインズマーケットインフォメーション」は、どちらも実際に行われた不動産の取引価格を調べることができます。リアルな情報と言えますが、大体の所在までしかわかりません。そもそもリアルな不動産取引は個別的な要因や事情、取引条件によって取引価格が大きく変わります。実際、条件を絞って検索してみても、取引価格や条件にかなりバラツキがあり、戸建の場合は単純に比較するのは難しいと言われています。ただ、マンションの場合は比較が簡単ですので、参考になるでしょう。
取引(成約)時期はできるだけ新しい方(1年以内)が望ましいですが、条件を絞りすぎると該当する取引が減り、データとしての信頼性が下がってしまいますので、少なくとも5件以上は該当するように条件を調整してください。土地では㎡単価、戸建とマンションは取引総額の全体の価格分布と、上限値、下限値をチェックします。土地は㎡単価で比較できるので、実際の取引価格が地価公示や相続税路線価より高いのか安いのかが確認できます。
参照:国土交通省「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00252.html
参照:国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
参照:国土交通省「不動産取引価格情報検索」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/
参照:全国指定流通機構連絡協議会「レインズマーケットインフォメーション」 http://www.contract.reins.or.jp/search/displayAreaConditionBLogic.do
自分で査定額を計算してみる
周辺相場の把握ができたら、査定額を計算してみましょう。簡単なのは固定資産税評価額を0.7で割る方法です。建物は違う数値の場合もありますが、自分でやる査定ですので、とりあえず簡便な方法で問題ないでしょう。ただし、マンションではこの方法は使えません。
実際に計算してみましょう。課税明細書に記載されている土地の評価額が1,750万円、建物の評価額が500万円だとします。ここで注意ですが、チェックするところは「評価額」で、「課税標準額」ではありません。土地建物の評価額の合計は2,250万円になりますから、2,250万円÷0.7で、約3,210万円が査定額になります。
計算したら、先ほど調べた周辺相場と比較してみましょう。不動産取引価格情報検索などで調べた戸建の取引で、地積、延べ床面積、築年数、駅からの距離が近いものがあれば、単純にその取引総額と比べます。実際の取引価格が査定額より高ければ、査定額はもっと高めになると考えられますし、実際の取引価格の方が安ければ、低めに考える必要があります。
マンションの場合は課税明細書から簡単に計算することはできませんが、Googleなどでマンション名と「中古 価格」などのワードで検索すると、現在売出し中の物件や過去の売買情報などが掲載されたページがヒットするので、より直接的に調べることができます。もしヒットしなくても、レインズマーケットインフォメーションでは実際の取引単価がわかりますし、不動産取引価格情報検索で取引総額も調べることができますので、参考にしてください。
まとめ
不動産の査定額を自分で計算する際に重要なのは、ある程度の価格幅をもって把握しておくことです。購入希望者はいくつかの候補物件から検討し、それらを比較しながら購入を考えることがほとんどなので、候補になりそうな物件の価格幅を知っておけば十分です。ただ、不動産の相場は社会動向などによって変わりますので、最新動向は常にチェックしておきましょう。
| 執筆者:岡田忠純 不動産鑑定士・不動産証券化協会認定マスター 不動産の鑑定評価はもちろん、不動産のキャッシュフロー分析や、取引、投資、開発などのアドバイザリーとして多くの実績がある、不動産のプロフェッショナル。官公庁からの依頼にも数多く対応している。 |

無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search