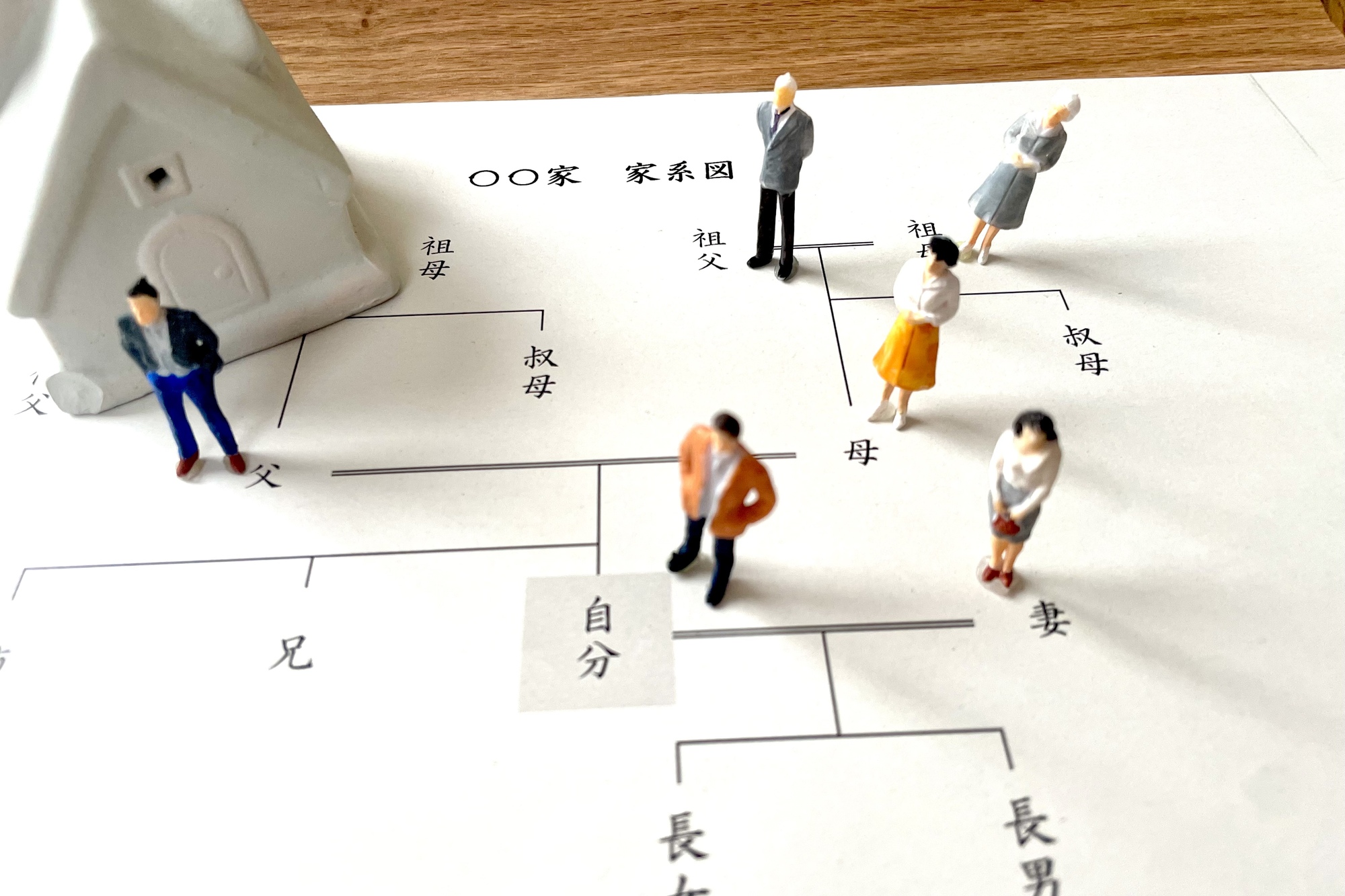不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
不動産賃貸業の経費と税金対策
最近は投資用に賃貸不動産を所有していたり、相続して賃貸不動産を所有していたりする方は多いのではないでしょうか。個人で所有していると毎年確定申告をして納税することになります。確定申告は、毎年賃貸料収入も変わらず、経費もほとんど変わらなければ、同じような作業を繰り返してしまうため、経費などを考える機会が減ってきていないでしょうか。
今回は不動産所得の経費を税法なども参考に再考し、さらに所得控除にも見落としがないかどうかを確認してみましょう。
所得税法上の経費
個人所得税の経費は、所得税法37条1項に総収入金額を得るために直接要した売上原価と販売費と一般管理費等の規定があり、これが毎年の通常の経費を算入する根拠になっています。
そのほかの経費に、同法49条には減価償却費、同法51条1項には不動産の取り壊し等の資産損失(建物除却損等)、同2項には貸倒れの規定があります。不動産所得の場合の貸倒れとは、未収家賃を回収できなかったケースがあてはまります。
また、同法57条1項には青色事業専従者給与に関する規定があります。
同法45条に家事関連費(生活費と絡んだ経費支出)を経費にできない規定があり、所得税法施行令第96条に「明らかに区分できる」場合以外には経費にできない規定があります。所得税基本通達37-2には、その年に債務が確定した金額を経費に算入できることが書かれています。
以上の内容をまとめると、
①その年に債務が確定し、
②家事関連費と明確に区分することができ、
③収入を直接得るために要した売上原価と販売費・一般管理費・減価償却費・不動産除却損・貸倒損失・青色申告の対象者で届け出を提出した場合の青色事業専従者給与
が経費にできることになります。
ただし、不動産所得の経費は、その賃貸不動産の規模によって下記のように取り扱いが変わります。事業的な規模の場合には下記の経費が認められていますが、事業的な規模に満たない場合には青色申告特別控除が受けられないなど、不動産除却損や貸倒損失の取り扱いも異なります。事業的規模とは、所得税基本通達26-9に一戸建ては5棟やマンションは10室以上という目安の記載がありますが、1棟でも大きなビルの場合には事業的規模になり、判断が難しいのが実情です。詳細な判断は専門家への相談をおすすめします。(※1)
(※1)出典:国税庁「事業としての不動産貸付けとの区分」
不動産所得で認められる経費
〇租税公課
租税公課は経費にできるものとできないものがあります。経費にできるものは下記のとおりです。
事業税
固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税のうち不動産賃貸収入に対応する不動産の税額
不動産賃貸にかかわる収入印紙
所得税法第45条に経費にできない租税公課があげられており、所得税や住民税を始め経費にできない税金が多いことが分かります。
〇損害保険料
賃貸をしている物件にかかわる火災保険などの損害保険料は経費にすることができます。また不動産収入のために従業員を雇っている場合、その従業員にかかわる福利厚生目的の生命保険料は経費にできるものもあるので、保険加入の際に確認しましょう。
〇減価償却費
所得税法第49条に規定されている賃貸不動産にかかる減価償却費は経費にすることができます。償却方法は、所得税は定額法を基本にしていますが、建物・建物付属設備・構築物以外の減価償却資産は届け出を提出することにより定率法などでの償却方法の選択が可能です。
また、減価償却方法は平成に入ってから計算方法や償却率に大きな変更があり、購入・建築年によって計算方法など大きく異なるので注意しましょう。(※2)
(※2)出典:国税庁「定額法と定率法による減価償却」
〇不動産除却損
所得税法第51条1項に規定されている賃貸建物等の取り壊しや除却などがあった場合には、不動産所得が事業的な規模の場合に限り、その年の全額経費にすることが可能です。事業規模ではない場合には不動産所得の金額を限度とするため、不動産所得の損失をほかの所得と損益通算することができません。
〇貸倒損失
所得税法第51条2項に規定されている未収賃貸料の回収不能額は、不動産所得が事業的規模の場合には貸倒れが発生した年の経費にすることが可能です。ただし、貸倒れにするための条件は厳しく、必ず貸倒れが発生した年内に経費にすることができる状態かどうかの確認が必要です。
〇修繕費
不動産所得にかかわる修繕費は金額が大きくなりがちで、資本的支出といって減価償却の対象にしなければならないケースもあるため注意が必要です。
所得税法施行令第181条にその内容があり、修繕をすることにより下記2つはその年に一括して経費にするのではなく、減価償却資産として減価償却費を経費にすることになっています。
①使用可能期間が長くなる場合
②資産の価値を増加させる場合
逆に言えば、単純に金額の大小ではなく修繕の内容にかかわるということです。意外と修繕費として一括経費にできるケースは多く、修繕の内容をよく検討しなければなりません。どちらか判断がつかない場合の規定は所得税基本通達37-12・13に具体的な処理方法の記載があります。(※3)(※4)
(※3)出典:所得税基本通達「資本的支出と修繕費等」
(※4)出典:国税庁「修繕費とならないものの判定」
〇借入金利息
不動産を取得するための借入金にかかわる支払利息は経費にすることができます。ただし、租税特別措置法第41条の4に規定されている不動産所得に損失がある場合の土地等の購入にかかわる借入金の支払利息は、不動産所得の損失をほかの所得と損益通算する場合にはその該当金額を損益通算することができません。
〇賃貸不動産にかかわる管理費・広告宣伝費
不動産業者等に支払う物件の管理費や賃借人を募集するため等の広告宣伝費、仲介手数料は経費にすることができます。
〇交通費・通信費・消耗品費・新聞図書費
不動産収入を得るためにかかった交通費・通信費・消耗品費・新聞図書費は経費にすることができます。しっかり領収書などを保管しておきましょう。
〇税理士・弁護士への支払報酬
不動産収入にかかわる経理や確定申告を依頼する税理士への支払報酬は経費にすることができます。また、賃借人とのトラブル解決など不動産収入のための弁護士費用も経費にすることが可能です。
青色事業専従者給与
所得税法第57条に規定する青色事業専従者給与は経費にすることができます。
給与の支払を開始して経費にする場合には、その年の3月15日までに届け出を提出しなければなりません。この場合、受け取った給与は給与所得として課税されることになり、控除対象配偶者や扶養親族になることができないため、給与支給額が配偶者控除や扶養控除以下の場合にはメリットがありません。
青色申告控除の変更
2020年から青色申告特別控除の額が変更になります。これまでの65万円控除は55万円に引き下げになり、代わりにe-Taxにより申告をした場合などには10万円の控除が加算されます。したがって、e-Taxにより申告書を提出していた場合の控除額はこれまでどおり65万円です。
青色申告特別控除は複式簿記により記帳をし、申告書を申告期限内に損益計算書と貸借対照表を提出した場合受けることができます。最近は会計ソフトなども使いやすくなってきており、複式簿記の知識をもっていなくても、結果として複式簿記により帳簿の記帳ができるものもあります。また、税理士などに依頼をした場合にも年間の報酬額が55万円以内であれば税金対策になり、また税金の相談もできるようになるので顧問契約を結ぶことを検討しましょう。(※5)
(※5)出典:国税庁タックスアンサー「青色申告特別控除」
所得控除
〇社会保険料控除
小規模事業共済・国民年金基金・確定拠出年金(企業型・個人型)に加入をした場合には、支払った額がその年の社会保険料控除の対象になります。それぞれ加入条件があるので、どれに加入することができるかを確認してから加入を検討しましょう。年金や一時金を受け取る際にも所得税の優遇措置がありますので、税金対策としてとても有効です。
〇医療費控除
医療費控除は1年間に支払った医療費を所得税の計算上で控除を受けられる制度です。年始から病院へ支払った領収書や薬局へ支払った医薬品の領収書は必ず保管しておきましょう。年が明けたら1年間の医療費の合計額を計算して、医療費控除の対象金額に満たない場合には使わなければ済むので、まずは年始から保存しておくことが大切です。
〇ふるさと納税
ふるさと納税は、ふるさと納税ワンストップ特例で住民税から控除を受けるか、寄付金控除として所得税の寄付金控除と住民税の税額控除を受けることができます。
ふるさと納税サイトから寄付をすれば、控除を受けるための書類を簡単に受け取ることができたりサイトのポイントがたまったりするので、寄付金控除以上のメリットがあります。
所得税は、法人税に比べて経費(損金)の範囲は狭く、不動産所得は特に経費の範囲が限定されます。ただ、ここで説明した税法の基本的な知識を持っていることで、経費の範囲を今より広げることができる場合があります。そのほかの所得控除も同様ですが、こまめに領収書を取っておき経理の帳簿をつけておくことが大切です。弁護士会や税理士会が定期的に無料相談会を行っておりますので相談してみましょう。
【執筆者プロフィール】須栗 一浩(税理士)
税理士法人エムエスオフィス 代表税理士
平成7年税理士登録・開業。平成27年より税理士法人へ合流。現在に至る。会社税務から個人の確定申告、相続税に至るまで活動範囲は広い。固くない、いつでも話せる税理士としてクライアントからの信頼は厚い。ファルクラム租税法研究会研究員

無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search