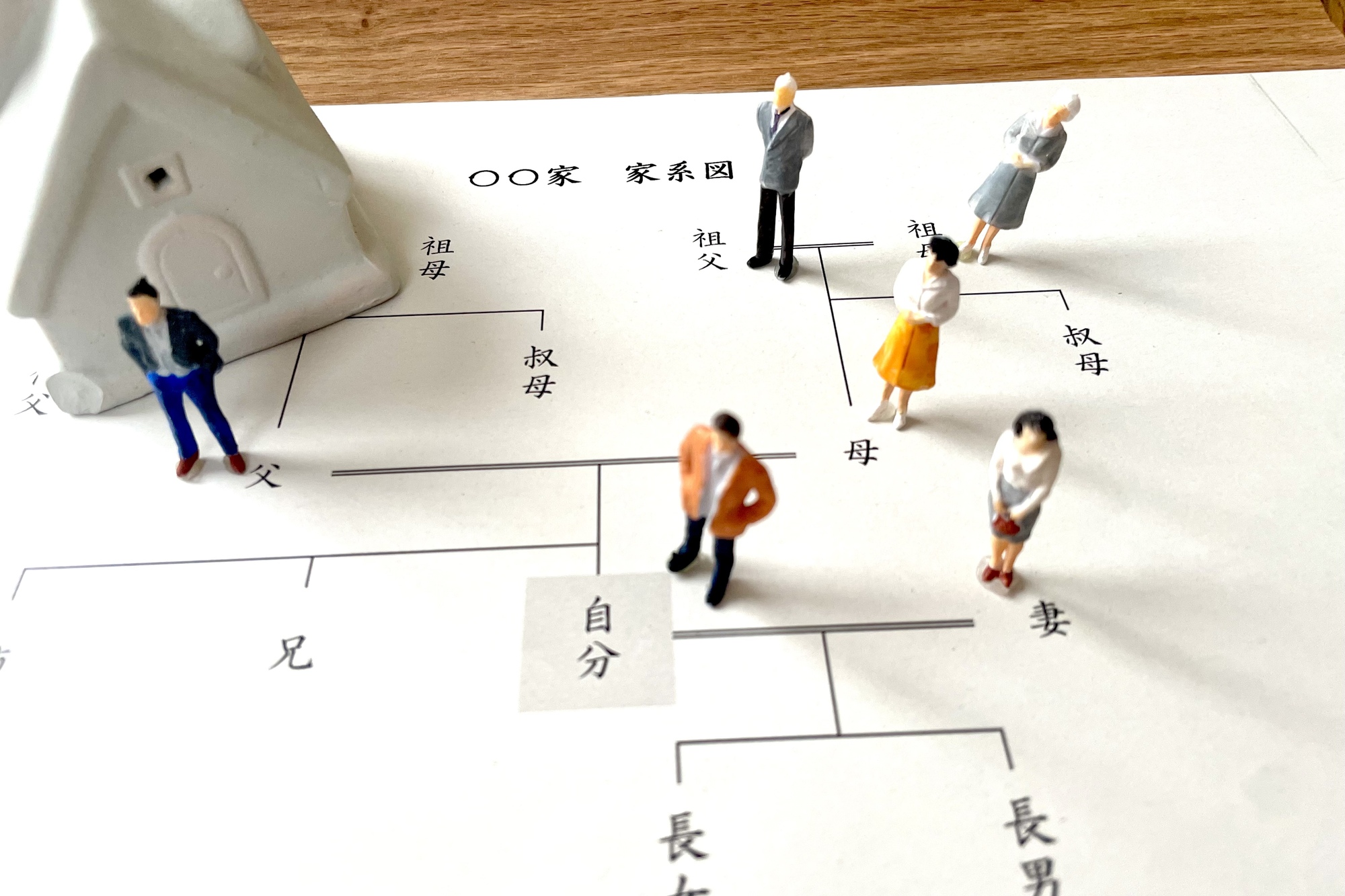不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
「配偶者居住権」とはどんな権利?
2020年4月に改正民法が施行されました。今回の民法改正では不動産に関係する改正点も多く、そのうち相続に関わる部分(相続法とも呼ばれます)に、新しい権利として「配偶者居住権」というものが新設されました。ここではこの「配偶者居住権」について解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続発生後も残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の持ち家にそのまま住み続けられるようにする権利です。これまでは残された配偶者にこうした権利がなく問題になることがありました。たとえば、相続税の支払いのために被相続人の持ち家を売却しなければならず、残された配偶者が住み慣れた住処を失うケースや、残された配偶者が住宅の権利を取得することができても生活費となる現預金などを相続できないといったケースです。
配偶者居住権が新設されたことによって、自宅の所有権を相続しなかった場合でも残された配偶者がそのまま居住できるようになり、ケースによっては生活費となる現預金の相続もできるようになります。
また別の見方をすると、配偶者居住権は「住宅を所有する権利」と「住宅に居住する権利」に分離し、そのうちの居住する権利部分ともいえます。
ここで少し具体的な事例で説明しましょう。
たとえば、夫が死亡し、相続人として配偶者の妻と子1人が夫名義の4,000万円の自宅と現預金2,000万円の計6,000万円が遺産として残されたとします。このとき、妻(母)と子の関係が悪く、子は母に「自宅に住み続けるなら家の権利は譲るが、自分の相続分は残された現預金と足りない分は母からお金でもらいたい」と主張しているとしましょう。
以前ならこのような場合、妻が自宅に住み続けるには家の所有権を持たなければなりません。妻と子の法定相続分は1/2ずつとなるため、妻が自宅を相続した場合、2,000万円の現預金は子に相続され、妻の法定相続分(1/2)の3,000万円を超える家の価値1,000万円相当を、妻が子に現金などで支払う必要があります。この場合、妻に1,000万円を支払う資力がなければ家の所有権を取得することができず、住み続けることができません。家を売却するか、仮に1,000万円を子に支払うことができても、その後の妻の生活費となる蓄えは減ってしまいます。
一方、配偶者居住権を活用した場合、妻と子双方の合意は必要ですが、妻は家に住み続けることができ、生活費もある程度を確保することができます。
例えば、自宅の配偶者居住権の価値を2,000万円、残りの所有権の価値を2,000万円とします。そうすることで、妻が居住権として2,000万円と現預金1,000万円の計3,000万円(1/2)を相続し、子が自宅の残りの所有権2,000万円と現預金1,000万円の計3,000万円(1/2)を相続するという形に分割することが可能になります。
このような分割形式であれば、妻は住み慣れた家に住む権利を確保しつつ、生活費となる現預金を相続することが可能になるほか、これまでなら自宅を売却しなければ解決しなかったケースでも配偶者居住権を利用することで、自宅の売却が免れることもあり得ます。
しかも、配偶者居住権は、遺産分割協議の選択肢、あるいは被相続人の遺言等によって残された配偶者に権利を取得させることができ、基本的に配偶者が亡くなるまで(終身)続きます。必要であれば権利期間を10年や20年のように定めることも可能です。
配偶者居住権の注意点
次に、配偶者居住権の活用にあたって注意すべき点について以下でみていきましょう。
・別居していた配偶者には認められない
配偶者居住権は、被相続人(亡くなった人)が所有している建物に相続発生時点で住んでいる配偶者に認められる権利であるため、別居していた場合は認められません。
ただし、被相続人が複数住宅を所有しており、いずれかの住宅に残された配偶者が別居して住んでいたような場合は、残された配偶者が居住している住宅について権利が認められます。
・配偶者居住権を登記すること
配偶者居住権は登記しておく必要があります。登記していないと、万一、建物の所有者がその所有権を第三者に譲渡した際、新たな所有者から建物の明け渡しを要求されても正当な権利を主張することができません。最悪、立ち退きとなる恐れがあります。なお、配偶者居住権の登記は、土地にはできず建物のみが対象となるので注意しましょう。
・居住を続ける配偶者には善管注意義務がある
配偶者居住権は、あくまで住む権利という利用権であるため、居住者は使用者として建物所有者に対する「“善良な管理者の注意”を払う義務」があります。(※1)(※2)
・相続税の課税対象になる
配偶者居住権は、居住権という財産的な価値があるため相続税の課税対象となります。所有権より低い価値となりますが、価値を勝手に設定することはできません。
・配偶者居住権は譲渡できない
配偶者居住権は、被相続人(亡くなった人)の配偶者だけに認められた権利であるため、その権利を売却など譲渡することはできません。また、相続した配偶者の死亡によって権利は消滅し、相続することもできません。
・2020年4月1日以降に発生した相続に適用
配偶者居住権は、2020年4月1日以降に発生した相続に適用されるため、それ以前に発生した相続には適用されません。また、遺言書もその作成日が2020年4月1日以降である必要があるため、この権利を活用した遺言としたい場合は、適用日以降の日付で遺言書を作成しなおす必要があります。(※3)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-16.htm
・建物の所有者に注意が必要
配偶者居住権は、被相続人が単独で所有、または被相続人と残された配偶者で共有していた建物でのみ認められます。例えば、自宅の建物を子と被相続人である父が共有していた場合は、配偶者居住権が認められません。将来、この権利の活用を想定する場合には、相続が発生する前に建物の名義をいずれか一方の配偶者名義とするか、配偶者間の共有名義としておく必要があります。
配偶者短期居住権との違い
配偶者居住権と同時に、配偶者短期居住権という権利も新設されました。この権利は相続の開始(住宅を所有する配偶者が亡くなった時点)から配偶者居住権が設定されるまでの間、一時的に残された配偶者が居住する権利がない状態になるのを補完するために用意された権利です。この権利には有効期限があり、「相続開始から6カ月」または「遺産分割によってその家を取得する人が決まった日」のいずれか遅いほうの期限まで認められます。
また、配偶者居住権は建物全体に及ぶ権利ですが、配偶者短期居住権は建物の一部である居住部分のみに認められる権利という違いがあります。(※4)
配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人の所有していた自宅に住み続けることで生活の安定を図ることを目的に新設されました。活用するにはいくつか要件があるため、相続発生前に建物の権利や遺言の作成日など要件を満たすよう準備しておく必要があります。
【執筆者プロフィール】
秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。
横浜国立大学卒業後、神奈川県住宅供給公社に勤務。その後不動産仲介会社等を経て、独立。現在は、自宅の購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う。その他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム等の執筆にも取り組んでいる。"

無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search