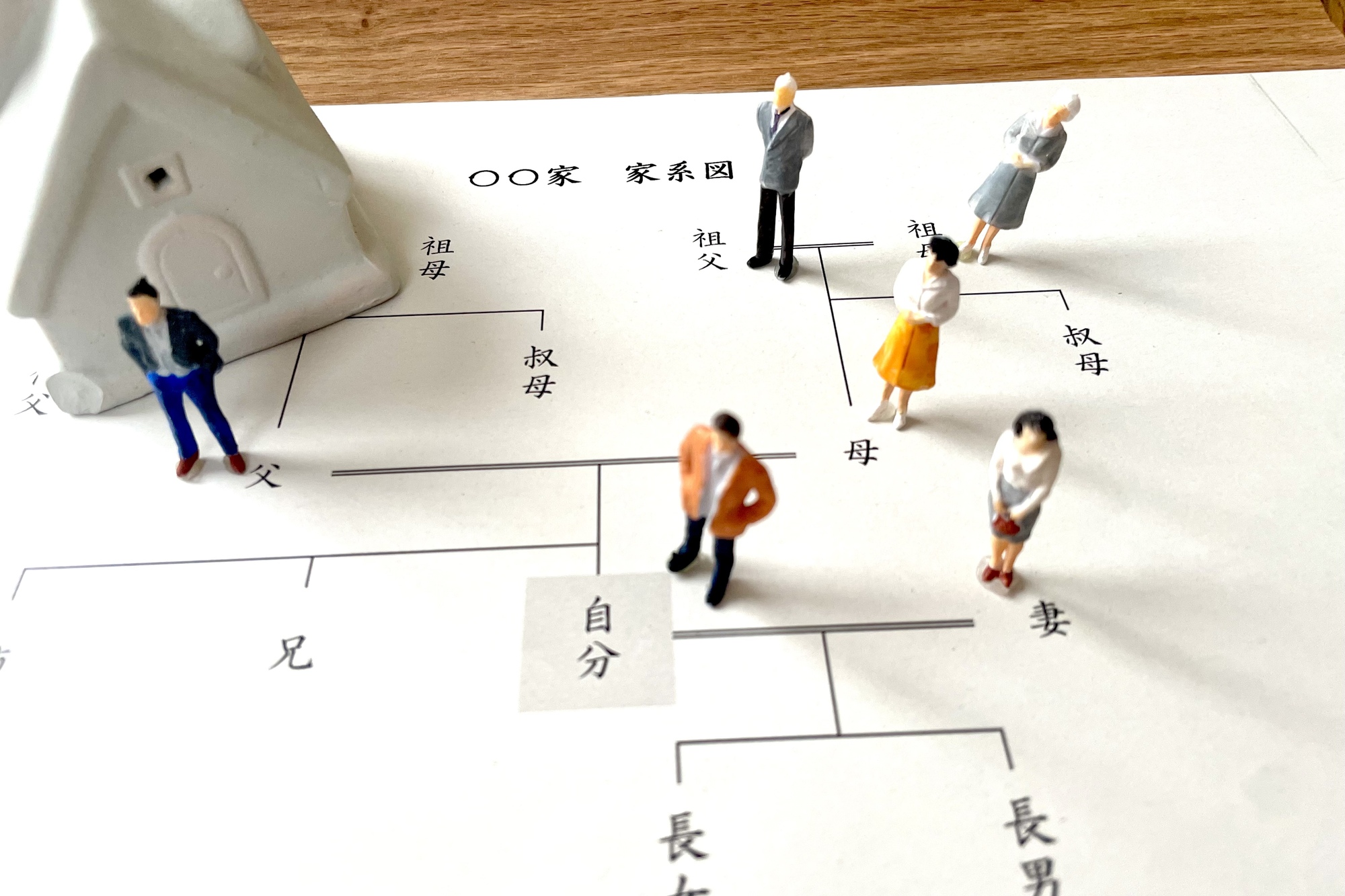不動産コラム
私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談
民放改正で新たに追加。不動産売買に関わる契約不適合責任とは?
2020年4月1日、民法が120年ぶりに改正・施行されました。今回の改正では不動産に関係する変更点も多く、中でも不動産売買に関わる部分として従来の「瑕疵担保責任」が新たに「契約不適合責任」という概念に改められました。今回は、新たに規定された「契約不適合責任」についてご紹介します。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、引き渡された目的物がその種類・品質・数量にかかわらず「契約内容に適合していない」と判断された場合に債務不履行となり、そのとき売主が買主に対して負う責任のことです。
不動産売買では、引き渡した土地や建物が契約書などの記載内容と適合していない場合に売主が買主に対して負う責任となります。従来の瑕疵担保責任では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に売主が負担する責任でした。隠れた瑕疵とは、代替えのきかない特定物である土地や建物の売買契約時点では、買主が知らなかった瑕疵(不具合等)で、かつ通常の注意力をもって発見できなかった瑕疵のこととなります。
それに対し、契約不適合責任では「隠れた瑕疵」だけでなく、「契約内容に合っていない場合」には売主がその責任を負うことになり売主責任の範囲が広がりました。
どこまで売主に責任を求めることができるのか
従来の瑕疵担保責任では、「隠れた瑕疵」があった場合に買主が売主に対して求めることができた請求権は「損害賠償請求」と「契約解除」の2つだけでした。一般的な債務不履行責任に認められる補修や代替物等の請求や売買代金の減額を要求することはできなかったのです。
契約不適合責任となったことにより、「損害賠償請求」と「契約解除」の2つの請求権に加え、買主は売主に対して「追完請求(補修請求)」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」が可能になりました。以下に追加された請求権について説明します。
追完請求(補修請求)
追完請求とは、引き渡した目的物が不完全な状態であったため、後から完全なものを求める請求権です。不動産売買であれば、例えば建物に契約で約束した状態とは異なる不具合があった場合に補修や修理などを請求できます。土地など不動産そのものは唯一無二であるため代替請求が難しいですが、設備など代替が可能な部分は代替請求することも可能です。代金減額請求
代金減額請求とは、前述の追完請求をしたにもかかわらず、売主が応じないときに代金の一部を返還要求できる請求権です。ただし、あくまで追完請求をしてその履行がない場合に請求できるものなので、いきなり代金減額請求することはできません。催告解除
引渡しを受けた目的物(土地や建物)に契約内容とは異なる不適合な部分があり、追完請求を行ったにもかかわらず、売主がそれに応じない場合には買主が契約を解除することもできます。したがって、売主が追完請求に応じない場合は、買主は代金減額請求か、催告解除が可能ということになります。無催告解除
引渡しを受けた目的物が契約不適合によって「契約の目的を達することができない」場合に限って、買主は催告せずに即時解約することができます。逆に多少の不具合で補修できる場合、無催告解除は認められません。 また、瑕疵や不適合があった場合に買主が売主に対して請求できる期間についても、瑕疵担保責任と契約不適合責任では異なります。瑕疵担保責任では「買主が目的物に瑕疵がある事実を知ったときから1年以内に契約の解除または損害賠償の請求権を行使」しなければなりませんでした。 一方、契約不適合責任では「買主がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知する」こととなり、権利の行使はその権利の種類によって5年以内、または10年以内となりました。このように買主が売主に対して権利を行使できる期間も買主にとっては有利なものに改正されたのです。 売主や買主は何に気を付ければよいのか 売主側としては、売買の目的物(土地や建物)の不具合などについて売買契約書等に詳しく記載することが非常に重要になりました。特に中古物件の売買契約の実務では、契約時に売買契約書と重要事項説明書のほか、添付書類として「物件状況報告書(物件状況確認書あるいは告知書とも呼ばれます)」と「付帯設備表」を売主が買主に交付します。 物件状況報告書では、売買対象の不動産である土地や建物の契約時点での状況、例えば以下のような状況を記載します。「建物の雨漏り」
「シロアリの被害」
「給排水管の故障」
「耐震診断の実施の有無」
「火災の被害」
「リフォームの実施」
などについて、
土地については
「地盤沈下の事実」
「土壌汚染の可能性」
「配管等の引込に際して第三者との関係」
付帯設備表では、建物に付属する設備の以下のような状況を記載します。
「給湯器の種類」
「エアコンの有無」
「引渡しの対象となる照明の位置やその数」
通常、この付帯設備表に記載する際、引渡しに際して不具合があるものはその不具合の状況を記載し、その不具合について交換や補修、あるいは撤去のみ行うなど細かく記載します。いずれも売主が売買対象の物件について、その時点で把握している状況を不具合なども含めて記載し、買主に告知するものとなっています。
今回の改正により、売主の引き渡す目的物に対する責任の範囲が広がったことから、これらの書面の役割も重くなったと言えます。後日、契約不適合と指摘されないためにも、売主として不具合も含めて細かく告知することが重要になります。
一方、買主側は売買契約書と重要事項説明書だけでなく、物件状況報告書と付帯設備表にもしっかりと目を通し、目的物である土地や建物の現状を理解することがポイントになります。ただし、書面だけではわからないことも多いので、必ず現地で実際の土地や建物を確認し、売主立ち合いのもと不具合などの状況について、不明点や気になる点は質問するなどして納得できるように確認しましょう。
また、取引実務では売買契約書に売主が責任を負う期間が定められるのが一般的で、物件によっては不適合責任免責となっている場合もあります。というのも、民法の規定通りの請求期間ではいつまでも売主が責任を追い続けることになってしまうからです。特に築年の相当古い物件では不具合も多く、その責任をいつまでも負うことが現実的ではありません。買主としては、売主が責任を負う期間がいつまでなのかもきちんと確認しておく必要があります。
まとめ
今回の民法改正は、売主にとっては責任の範囲が広がり、買主にとって有利な改正となりました。しかし、不具合があった場合に買主が売主に対して請求できる期間が契約書で一定期間内に制限されることが一般的です。そのことを意識して、買主としては引き渡し後速やかに不具合などの確認することを心がけるようにしましょう。
執筆者:
秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。
横浜国立大学卒業後、神奈川県住宅供給公社に勤務。その後不動産仲介会社等を経て、独立。現在は、自宅の購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う。その他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム等の執筆にも取り組んでいる。
無料査定・売却のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ
店舗から探す
Store search
Store search