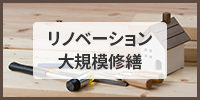019
消費税とは
|消費税の種類や納税の流れ、問題点を解説

日本では、2019年10月に消費税率が8%から10%になり、所得税もじわじわと増税となり、最近は国際的な流れで法人税率のアップについても話が及んでいます。そのような税金の中でも、「消費税」は最も身近な税金であり、選挙の公約には必ず消費税に関するものが掲げられています。
今回は、日本の消費税は税金の中でどう分類されているのかについて説明します。身近ですが意外と知らないことも多い日本の消費税の理解を深めましょう。
直接税と間接税
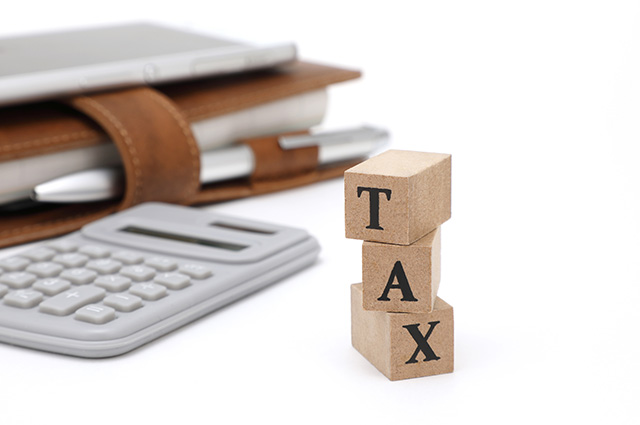
まずは、税金の徴収と納税の方法から税金の分類について説明します。徴収と納税から分類すると、税金は「直接税」と「間接税」に分けられます。
直接税
直接税とは、納税者が税金を国や地方自治体へ直接納めるものをいい、税負担をする担税者(納税者)と税金を納める納税義務者が同じ税金です。所得税、法人税、相続税、自動車税、固定資産税などが直接税に当たります。
直接税は、所得や財産価値の大小などに応じて税率を変える「累進課税制度」を取り入れることが可能で、所得などの大きさによって変わる担税力(税を負担できる能力)に応じて税負担を増やすことができます。これは、富の再分配など政策的な要素を取り入れることを可能にします。
間接税
間接税とは、納税者が国や自治体へ直接納めるのではなく、納税義務者が税金を徴収して、納税義務者が国や自治体へ納めるものをいいます。日本の消費税や酒税などが間接税に当たります。
間接税は、基本的には納税者の状況に応じて税率を変更することが難しく、一定にするか、消費税の軽減税率や酒税の酒の種類によって税率を変える程度しかできません。
付加価値税や支出税
税金には、課税の対象による分類もあります。主に「①所得から ②消費である支出を引くと ③貯蓄が残る」という個人の経済の流れのどこに課税するかという分類です。
①が課税の対象だと所得税、②が対象だと支出税、③が対象だと(一般的には)相続税となります。それぞれの税について見ていきましょう。
①所得税
所得に課税をするという考え方が「所得税」です。一番広い範囲に課税をすることになることから、公平性が高いと言われます。所得の大きい人ほど税率を高くして、富の再分配を促すという垂直的な公平という意味でも優れていると言われています。
日本の税制は長いあいだ、所得に課税するという形態をとってきました。ただ、経済構造の複雑化や所得概念の変化、もともと抱える累進課税の限界などの所得課税の問題点も多くあり、日本の税制は所得課税から徐々に移行してきています。
②支出税
消費に対する課税は、消費部分に課税をするという考え方です。「支出税」と呼ばれ、本来の消費への課税は直接税に分類されます。
支出税は生活水準に合わせて累進課税制度の導入も可能であることから、所得税に代わるものとして経済学上は長く提唱されてきました。しかし、実際には各個人の消費の把握が非常に困難なことから、これまで導入された国はありません。
大まかな計算方法は、所得の証明金額から年間の貯蓄の増加額の証明金額と負債の増加額の証明金額を加減して、差額を消費として課税するというものです。
現在の日本の消費税は、消費に課税をするという面では共通します。ただ、日本の消費税は事業者が納税事業者となる間接税の形態をとっています。そのため、本来の支出税のような累進課税方式を組み込むことはできず、よく言われる逆進性のある税制になってしまっています。
日本の消費税はヨーロッパで広く導入されている「付加価値税」に分類されます。世界的には同様のさまざまな仕組みがあり、広く導入されています。広く均一課税をすることが可能で、水平的公平という考え方により、同じ消費金額の納税者の税率は一定で課税されます。
③相続税ほか
貯蓄の増加に対する課税は、実際には預金の増加額に対する課税があるわけではありませんが、一般的には資産の無償取得に対する「相続税」がこれに当たると言われています。
そのほかで資産に対する課税は、資産の保有に対して課税される「固定資産税」や「自動車税」などがあり、資産の移転に対して課税する「登録免許税」、「印紙税」、「不動産取得税」などもあります。
日本の消費税の納税の流れ

消費税の納税義務者は、「生産・流通・販売」の全段階の売上に課税され、仕入に関わる消費税を控除した金額を納税する仕組みになっています。消費税額は次の段階へ転嫁され、最終的に消費者が負担することになります。
例えば、何かを製造して最終的に消費者に販売する場合、以下のような納税の流れになります。
①製造業者
卸売業者に対する売上100円に対する消費税10円を卸売業者から徴収して税務署へ納税
②卸売業者
小売業者に対する売上200円に対する20円を小売業者から徴収、仕入原価100円に対する消費税10円を差し引いて10円を税務署へ納税
③小売業者
消費者に対する売上400円に対する40円を小売業者から徴収、仕入原価200円対する消費税20円を差し引いて20円を税務署へ納税
④消費者
440円で商品を購入して、結果として40円の消費税を納税
実際には、事業者は仕入以外にも経費がかかっているため、その経費に対する消費税も控除して納税します。このように事業者は消費税を負担することなく、消費税の預かりと納税を繰り返し、最終的に消費者が納税することになります。
日本の消費税の問題点

一見、簡単で理想的に思える消費税の仕組みですが、特例措置を入れることによる課題点も多くあります。
免税事業者
売上が1,000万円を超えた年の翌々年から消費税の納税義務者になります。その場合、消費税を計算し、申告と納税をしなければなりません(2025年2月現在)。消費税でいう「事業」は、法人税や所得税などでいう事業とは少し異なり、本人の意思や規模に関係なく、物を販売したり、サービスを提供したりして対価を受けるすべてが対象になります。
しかし、一般の人がオークションサイトでいらなくなった物を売却した場合まで消費税を徴収して申告と納税しなければならないというのは、現実的な話ではありません。
また、消費税の計算はとても細かい作業で、手書きの計算では時間もかかる上に正確な計算はなかなかできません。そこで、小規模な事業者は消費税の納税申告義務を免除するという制度が導入されています。
ただ、免税事業者は消費税を徴収しないことで、売上が1,000万円以下だということが取引先にわかってしまうことがあります。規模が小さいという理由で取引から排除されないようにするために、免税事業者も消費税を徴収しているような請求書などを発行している場合が多くあります。免税事業者は、納税をすることのない消費税相当額分だけ利益を多くあげることになるため、当初より批判がありました。
2023年10月よりインボイス制度が始まりました。この制度では、消費税の納税事業者は税務署へ消費税の事業者登録を行い、登録番号を請求書などに記載することが決められています。これによって登録番号を持っていない事業者への消費税の支払いは不要になるため、免税事業者は消費税相当額の利益をあげられなくなるということになっています。
簡易課税制度
簡易課税制度は、消費税の納税義務者の中で、売上が5000万円以下の事業者は簡易課税制度を選択することで、課税仕入(消費税のかかる仕入や経費)に関する計算をすることなく、事業区分ごとに決められた売上に対する仕入率を使って控除する消費税額を計算し、納税することが認められています。
この制度も売上の少ない事業者の事務負担を軽減するために導入されています。仕入控除率は、卸売業の90%から不動産業の40%までの6段階です。
しかし、この制度を適用することで簡易課税を選択した事業者は、一般課税の納税額より少ない納税で済むことが多く、いわゆる益税が発生するために批判の声があがっています。
ただ、簡易課税を選択することで支払いに関する消費税の事務負担がなくなるため、インボイス制度が導入された現在では、さらにこの制度を選択する事業者が増えることが見込まれます。
まとめ
消費税における納税義務者側の事務負担は大きく、日本の消費税の法体系では、消費税の徴収漏れなどが見つかった場合には消費者側へ転嫁することができず、納税義務者の負担になってしまいます。この点は、単純な間接税とは言えない制度になっています。
ただ、今後の日本の税収を担っていく税として、消費税に重要な役割があるのは間違いありません。間接税は税負担を感じにくく、多くの方が消費税を年間いくら納税しているかを把握していないでしょう。納税の義務を負っているわけですから、消費税の仕組みを理解して、納税意識を持つことはとても大切です。
執筆者:須栗 一浩 税理士 税理士法人エムエスオフィス 代表
1995年に税理士登録し、これまで個人法人の関与先クライアントは500件をこえる。個人事業の開業から、法人設立、相続税まで含めたトータルのコンサルタント業務をおこなう。
企業のICT化も推進し、クライアント企業への導入も進めている。ファルクラム租税法研究会研究員
大和ハウスリアルエステートでは、東北北海道エリア・関東エリア・中部エリア・関西エリア・中国エリア・九州エリアの不動産情報(マンション・戸建て・土地・収益物件)をご提供。中古物件・住宅を地域や沿線、駅から簡単に検索でき、エリア別の特集情報やタワーマンション・中古マンションギャラリーなどさまざまな不動産情報が満載です。不動産売却をご検討の方向けのサポート情報も掲載しております。また、初めての不動産購入や住み替え、住宅売却の参考になるコンテンツも充実。マンション・戸建て・土地など不動産の購入・売却なら大和ハウスリアルエステートへお任せください。