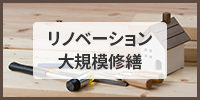020
不動産管理会社の設立の流れとは。
設立の3方式とメリット・デメリットも解説
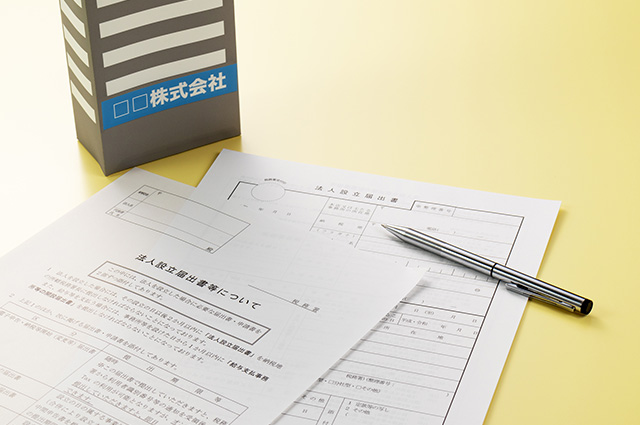
すでにマンションなどの貸家を所有していて、家賃収入を得ている方もいれば、投資の一つとして賃貸不動産の購入を検討している方もいらっしゃるでしょう。不動産投資は、入居率と修繕のリスクが主な注意点ですが、比較的安定した収益を生みます。今回は、不動産の賃貸収入と賃貸不動産を管理する会社の設立について説明します。
・そもそも不動産管理会社とは

不動産管理会社とは、不動産収入を得る際の1つの形態です。不動産収入を得る仕組みは、大家さんである不動産所有者と借主とのあいだに法人を挟んで、主に家賃収入を法人経由で受け取る形になります。不動産管理会社を通して賃貸を行うことで、節税対策になるとともに、リスク対策や相続対策にもなります。一定以上の規模の大きな不動産を所有している場合には、よく使われるスキームです。
不動産管理会社の形態は、主に管理委託方式、建物所有方式、サブリース方式の3つがあります。ここから、それぞれの方式について解説します。
1. 管理委託方式

不動産オーナー(以下、オーナー)と借主のあいだに入り、もしくはオーナーの補佐的な位置にいて、家賃の入金管理や小規模な修繕の管理などを行う管理を委託する方式を「管理委託方式」と呼びます。
管理委託方式のメリット
最も容易に行うことができる方式で、デメリットは少なく、一定以上の規模がある場合には効果があります。オーナーは不動産管理会社へ管理料の支払いを行い、管理会社はオーナーへ給与を支払うことで、不動産所得のみでは受けることのできなかった給与所得控除というみなし経費の控除を受けることができます。
また、家族で管理業務を行う場合には、家族への給与の支給を行うこともできるため、さらに給与所得控除を受けられるとともに、所得の分散による所得税累進課税の低減効果もあります。
所得税より法人税の税率が低くなるため、オーナーの課税所得が大きい場合には、管理会社へ管理料を支払い、法人で利益を出して法人税を納税するほうが納税額は少なくなります。
会社への出資金をオーナーではなく、親族が出して会社を設立すれば、会社の利益は出資者である親族のものになるため、オーナーの相続財産からは除外することができます。
不動産所有者が高齢で不動産の管理業務を行えない場合には、親族が不動産管理会社の役員になり不動産賃貸管理をすることができます。
給与として支給した場合、社会保険への加入が必要となりますが、給与の金額が少ない場合には、国民健康保険料と国民年金より社会保険料の支払いが少なくなるケースあります。試算をしないで給与を支給すると社会保険料が高くなり、給与として支給することがデメリットになるケースもあるので注意が必要です。
管理委託方式のデメリット
賃貸料収入のうちの一定割合を管理費として会社へ支払い、会社は管理料のみが収入となります。そのため、賃貸不動産の規模が小さい場合には、会社が受け取る管理料も小さくなり、会社として成り立たないケースがあります。もし法外な管理料を個人の経費にした場合は、税務上で経費を否認されるケースがあるため、世間の一般的な割合である必要があります。
また、勤務がなかったり、少なかったりする親族へ多額の給与を支払った場合も、給与を否認されることがあります。
しかし、会社を運営するためには、決算時の法人税や税理士への申告書作成報酬などの必要経費が発生するため、これらと管理料収入が見合わない場合には設立しても意味がありません。
不動産管理会社の法人税の申告をしなければならなくなるため、個人の確定申告より手間のかかる会社の経理を行っていく必要があります。会社の経理をやり切れない場合には、管理会社設立は諦めたほうがいいかもしれません。
2. 建物所有方式

不動産所有者から建物を買い取るか、土地を借りて新しく建物を法人名義で建て、賃貸する方式を「建物所有方式」と呼びます。
建物所有方式のメリット
建物が会社の所有になるため、不動産所有者の財産から除外され、相続税対策になります。
また、賃貸料収入は会社へ直接入ってくるため、不動産の規模に関係なく賃貸料収入の範囲で勤務に応じた給与の支給が可能になり、親族への所得の分散効果はより大きくなります。
建物所有方式のデメリット
建物を会社で所有する場合には、借地権が発生することになり、オーナーへ借地権設定の対価を支払う必要があります。対価を受け取ったオーナーには譲渡所得が課税されるため、大きな納税が必要になります。対価を支払わない場合にも、借地権の認定課税といい、法人が借地権の贈与を受けたものとして利益に計上しなければなりません。
これを回避するために、相当の地代という通常の地代より高い地代を支払うか、「無償返還の届出書」を提出すると認定課税は行われませんが、借地権の価額もゼロとなり、相続税対策にはなりません。
借地権の問題は地代の設定なども含めて、とても難解なため、この方式をとる場合には事前に税理士へ相談しましょう。
建物を買い取ったり、新築したりするための資金が必要になるため、オーナーや金融機関からの借り入れが必要になります。受け取る家賃で返済ができないとこのスキームは成り立ちません。
3. サブリース方式

不動産所有者から不動産管理会社が建物を一棟借りて、他へ賃貸する方式を「サブリース方式」と呼びます。この方式は基本的に管理委託方式とあまり変わりません。ただ、建物を一棟借りることになるので、不動産の規模が大きく、設立する法人に潤沢な資金が用意できる場合には、法人の資金を使って賃貸を事業として展開していくことも可能です。その場合には、オーナーではなく会社の財産となるので、相続税対策になります。
・不動産管理会社設立までの流れ
続いて、不動産管理会社を設立する流れについて解説します。
設立にあたって決めなければならないこと、必要なもの
不動産管理会社の設立は、通常の法人設立と変わりはありません。まず、決めなければならないことは、「会社の種類」「会社名」「決算月」「役員」「本店所在地」「出資者」「資本金の金額」などです。
会社の種類は、株式会社か合同会社のどちらかになりますが、不動産管理会社として親族間で会社を設立する場合には、合同会社をおすすめします。株式会社は、設立後も役員の変更登記や決算の公告などしなければならないことがあり、手間と費用がかかります。これに対して、合同会社は組織がかなり簡略されているため、株式会社に比べて手間がかかりません。
役員は、オーナーか実際に勤務する親族がなるのがいいでしょう。ただし、合同会社の場合には、役員と出資者が同じ(社員)であるため、もし、経営に関わらない場合には、登記の仕方が変わってきます。
資本金の金額は1円から可能ですが、会社設立の費用が捻出できないため、実際には最低限の設立費用以上の金額が必要です。
会社設立登記に必要なものは、「資本金」「会社の代表印」「代表者の印鑑証明書」などです。会社の代表印は、決められた規格にしたがって新しく作りましょう。印鑑の材質にはさまざまなものがあり値段も幅広いですが、最近は代表印を押す機会も減ってきているため、高価な印鑑である必要はないでしょう。
設立費用
会社設立のための費用は、登録免許税や定款の認証費用などが最低限かかり、その他に司法書士や行政書士へ依頼する場合には報酬料金もかかります。最低でも株式会社で約24万円以上、合同会社で10万円以上かかり、これに専門家へ依頼した場合の手続き費用が追加になります(専門家へ依頼して電子認証で定款認証を行った場合はもう少し安くなります)。
早く確実に会社を設立するには、専門家へ依頼するほうが安心です。ただ、時間もあって、設立の手続きの勉強もしたいということであれば、ご自分で設立手続きを行うこともできます。参考になるサイトも多くあるので、ご覧になってみてください。
設立後の手続き
法人の設立登記が完了したら、税務署や都道府県や市町村の役所へ設立の届出を提出しなければなりません。青色申告で申告をする場合には、設立後3カ月か会社の決算のどちらか早い日までに税務署へ申請の届出を提出しないと、最初の期は青色申告で申告することができなくなります。
設立時に提出する書類は、国税庁や各役所のホームページからダウンロードして作成することが可能です。通常の会社の税務署へ提出する書類は以下の通りです。
①内国普通法人等の設立の届出
②青色申告書の承認の申請
③給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
③と④は会社が給与を支払う場合に必要な書類で、④は給与を支払った際に徴収する源泉所得税を半期に一度まとめて納めるための書類です。これを提出しなかった場合には、給与を支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければなりません。この書類を提出すると、1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税を1月20日までに納めることになります。
この手の提出書類は記入するコツというのもあるので、決算時に申告を税理士へ依頼することを考えているのであれば、会社の設立前から関わってもらって、設立時の書類作成や提出も依頼したほうが安心です。
まとめ
不動産管理会社は、管理形態はもちろんのこと、役員や出資者など会社設立前にメリットやデメリットを確認し、それぞれの事情に沿って決めていくことがとても重要です。ネットや書籍の情報だけで設立すると、予定外の税金が必要になったり、資金面で会社の運営ができなかったりする可能性もあります。あらかじめ専門家に相談して、状況に合った不動産管理会社を設立しましょう。
執筆者:須栗 一浩 税理士 税理士法人エムエスオフィス 代表
1995年に税理士登録し、これまで個人法人の関与先クライアントは500件をこえる。個人事業の開業から、法人設立、相続税まで含めたトータルのコンサルタント業務をおこなう。
企業のICT化も推進し、クライアント企業への導入も進めている。ファルクラム租税法研究会研究員
大和ハウスリアルエステートでは、東北北海道エリア・関東エリア・中部エリア・関西エリア・中国エリア・九州エリアの不動産情報(マンション・戸建て・土地・収益物件)をご提供。中古物件・住宅を地域や沿線、駅から簡単に検索でき、エリア別の特集情報やタワーマンション・中古マンションギャラリーなどさまざまな不動産情報が満載です。不動産売却をご検討の方向けのサポート情報も掲載しております。また、初めての不動産購入や住み替え、住宅売却の参考になるコンテンツも充実。マンション・戸建て・土地など不動産の購入・売却なら大和ハウスリアルエステートへお任せください。